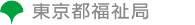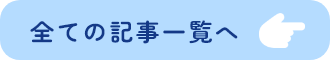第18回 記事言葉やふるまいを大切にした保育

こちらの園では、保育士が丁寧な応対的なかかわりをすることを、とても大切にしています。子供たちが人とかかわることを楽しみながら、自分の気持ちを伝えようとする表現力を育むためには、毎日の保育の中で、保育士の言葉かけやふるまいを丁寧にすることが重要と考えているからです。子供たちは1日の多くの時間を保育園で過ごすため、保育士の何気ない振る舞いをよく見ています。
例えば、遊んだ後の片付けの時に、保育士は子供たちが組み立てたブロックを一つひとつほぐしながら「やさしくね」と言葉を添えて片づけていると、子供たちは一緒に丁寧にほぐして片付けるようになります。何かを相手に渡すときに、必ず両手を添えて「はい、どうぞ」という振る舞いを、保育士が常日頃していると、受け取るときに子供が両手で受け取るようになります。子供同士でも、両手で「はい、どうぞ」が身に付いて、受け取る子供も両手で受け取るようになります。

また、全園児が集まって誕生会を開いたときのことです。誕生会担当のリーダー保育士が子供たちの前で笑顔で話しかけ、誕生日の歌を歌ったり、誕生日を迎えた子供の紹介をします。子供の側に、他の保育士が座って笑顔であたたかい雰囲気を作っていると、子供たちは安心して自分の気持ちを表現できます。保育士の何気ない言葉やふるまいが、子供たちの育ちに大きく関わっているのです。
保育士は子供たちに話しかけるときに、早口にならない、大きな声を出さないことを大切にしています。この園では、子供たちにも声の大きさのイメージを分かりやすく伝えるイラストを用いて声の大きさを可視化しています。
興奮した子供が大声で話しているとき、保育士は静かな口調で話しかけ、「ありさんの声でお願いします」と対応します。その子供は、気持ちを落ち着かせてから、声を落として話し始めます。保育室には声の大きさの段階を表した絵があり、子供たちは遊びながら、次第に声の大きさを使い分けるようになるのです。
このページをシェア