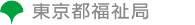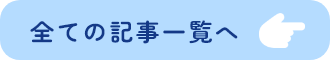第22回 記事子供も大人も経験して学びながら成長する保育

保育の現場では、大人にとってはあらかじめ予想がつくことでも、子供にとっては初めて経験することが多くあります。そのような時に、保育士は、先回りして言葉がけをするのではなく、子供自身が“自分で発見して気付くこと”を大切にしています。
例えば、絵の具遊びをするときに、保育士は「赤と青が混じったら何色になるでしょうか?」「どんな色に変わるかな?」といった言葉かけはあえてしないようにしています。それは、自分で経験して気付き、感じ、覚えていくことによって、子供の探求心や成長が深まるきっかけになるのです。
お散歩や外遊びでは、転ぶことが多々あります。そんな時、一般的にはすぐに駆け寄り「大丈夫?」と声をかけてその子の体を起こしてあげたくなる気持ちになります。ただ、保育士の場合はすぐに手を差し伸べるのではなく、その子がどうするかを、まずは見守ります。泣きながらも自分で立ちあがろうとする子、まだ遊びたいから泣かずにすぐ起き上がって遊び続ける子、友達が駆け寄って声を掛けられることで涙が収まる子等、様々な子供の姿がみられます。すぐに大人が手を差し伸べるのではなく、子供の力を信じて見守ったうえで個々に寄り添った対応をすることが大切です。
そうすることで子供の自立心が育まれ、保育士も子供の成長に気付くことができ、新たな保育へ繋がっていきます。

経験から学び、気付くことの大切さは子供だけでなく、大人に対しても当てはまります。
ある日、保育室から子供の声よりも大人の声の方がよく聞こえる場面がありました。保育士が子供たちについ先回りして話しかけ、大人主導の保育になっていると、子供の声よりも大人の声の方がよく聞こえることがあります。
一方、別のクラスでは、子供たちに指示したり先回りするような保育士の声掛けが見られず、子供たちがいきいきと遊びに熱中している様子がありました。
園長は保育士の声がよく聞こえている保育室の状況を見守りつつ、保育士に気付きを促す声掛けをしました。その保育士は、他のクラスの保育士の姿も見て、自身の子供への関わり方を振り返り、声掛けの仕方を工夫することで、子供の声がよく聞こえる保育室になりました。
保育士には保育の経験や知識の引き出しが豊富にあります。それを言葉にしてすぐに伝えるのは簡単ですが、他の保育士から先回りして伝えられてばかりいると、「自分で経験した保育」ではなく「人から言われたことをやる保育」になり、考えることが少なくなってきてしまいます。緊急事態においては例外もありますが、基本的には保育者自身も経験から学ぶことを大切にしています。
うまくいかなかったら次はどうしたらいいか?今度はこうしてみよう…というように、自分で考え経験を積み重ねていくことによって、少しずついろいろな保育場面での対応を身につけていき、その結果保育の引き出しが増えていくのです。
このページをシェア