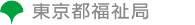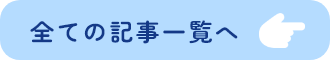第21回 記事食に関する様々な連携
保護者の負担を減らす離乳期の食材チェック

この園は0歳児から2歳児までの乳幼児が在園しています。
この時期の食事は母乳やミルクの授乳期から離乳期を経て幼児期へと移行していきます。一人ひとりの子供の発達段階などを鑑みて進める中で、家庭と保育園との連携は必要不可欠です。
離乳食では、完了期に進めていくために、様々な食材になれるようにすることが大切です。こちらの園では、食物アレルギー対応のために、子供が初めて食べる食材は、まずは家庭で食べてみて、安全が確認されたものから提供するようにしています。そのために献立表を事前に示し、家庭で試してほしい食材は栄養士から保育士を通じて保護者に伝えます。園で使われる食材は数も多くひとつひとつ試すには負担になってしまうため、ベビーフードをおすすめし、保護者の負担感が軽くなるようにします。また、ベビーフードには原材料が記載されているので、園から示された食材が入っているか確認することができます。そのように保護者に伝えると、「あ、食べていました。」となることもよくあります。食材チェックの方法を工夫することで、保護者の負担を少なくすることができるのです。
「園リーダー」は保育士と栄養士が連携

こちらの園では、栄養士が食事の時間に園児たちが食事をしている様子をいつも見ています。いろいろ話しかけながら、一人ひとりの様子を観察します。実際に食事中に子供と関わりながら様子を観察していると「この子はこれぐらいの大きさにすると手づかみしやすいのだな」「この子はご飯とおかずが一緒に盛り合わせていると食べたくないのだな」など調理の時に具体的にイメージすることができ、より子供に寄り添った食事の提供が実現していくのです。
この園では、毎月1回、給食会議を行い園児一人ひとりの子供の発達状態や食事について話し合います。歯の生え方の共有や、食具がどれくらい使えるようになっているか、離乳食の段階がその子の発達段階に見合っているかなど、園児それぞれの記録を基に綿密に話し合っています。保育士、栄養士それぞれ想いがあり、お互い遠慮せず伝え合うことでより良い保育・食育につながっていくのです。毎月の会議で記録されているノートには、子供にとってより良い食事環境を作ろうという保育士、栄養士それぞれの想いがたくさん詰まっています。
このページをシェア