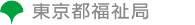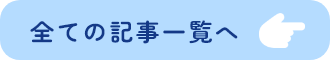第34回 記事保育者同士のコミュニケーションを通じた成長と信頼関係の構築 ~園内研修の取り組み~
心地よいコミュニケーションを育む保育園内研修の取り組み

保育者同士の心地よいコミュニケーションは、保育の現場で非常に重要な役割を果たします。こちらの保育園では、職員同士の対話を活性化し、子供理解を深めるための貴重な機会として、月に一度、子供の写真などを持ちより、ドキュメンテーションの作成を通した園内研修を行っています。
保育年数やキャリアに関係なく、新卒の保育士でも参加しやすいように、まずはシンプルで感動しあえるエピソードを選び共有します。1つのエピソードを通して感じた子供たちの生き生きとした姿や心を揺さぶられたことなどを語り合うことで、お互いの保育観を知りながら、子供の成長や環境構成などについて深く語り合うことができています。
また、職員が具体的に困っていることや知りたいことについても、園内研修で取り上げるようにしています。そして困りごとが園内だけでは解決しない時には、外部の専門家を招いて研修を行い、専門的な知識を得る機会を作っています。
例えば、園の看護師が保育士から小さい男の子のプライベートゾーンのケアについて相談を受けた際には、看護師が調べた情報を基に専門家を招き、具体的なケア方法を学びました。このような研修では、職員のスキルアップだけでなく、保護者や地域にも声をかけて一緒に学び、つながりを持つことにも寄与しました。
子供たちを取り巻く環境のなかで、保育士だけでなく、看護師や栄養士、保育補助等、資格に関係なく、1人ひとりが保育者として専門的な知識や経験を共有し合いながら子供も大人も育ちあえるように意識することが大切です。
保育者同士のコミュニケーションを通じた成長と信頼関係の構築

職員同士のコミュニケーションを円滑にするためには、意見を出しやすい環境を整えることが重要です。例えば、付箋に意見を書いて出す方法や、小グループでのディスカッションなど、様々な工夫をしています。これにより、ベテランと若手の保育士が対等に意見を交換しやすくなります。
さらに、職員の成長を促すために、発表の機会を設けることも効果的です。新卒の保育士が自分の保育について発表することで、自身の成長を実感し、他の職員からのフィードバックを受けることができます。これにより、職員同士が互いに認め合い、育ち合う文化が醸成されます。
新人職員の考えを知ることで、ベテラン職員も新たな気付きを得て、その考えを共有する事ができます。その逆もあります。このようなやり取りをすることにより職員全体が目指す保育の方向性を確認し、環境構成や保育者の配慮などについても、大事にしたい点をすり合わせることができるのです。これにより、職員全体が新たな視点を持ち、保育の質を向上させることができます。
保育者同士のコミュニケーションは、単なる情報交換にとどまらず、職員の成長や保育の質の向上に直結します。園内研修や日常の対話を通じて、職員同士が互いに学び合い、支え合う環境を作ることが大切です。これにより、子供たちにとって最良の保育環境が提供されるのです。
このように、保育者同士のコミュニケーションを重視することで、保育の質を高め、職員同士の信頼関係を築くことができるのです。
このページをシェア