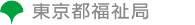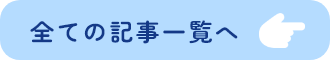第12回 記事「保育自慢会議」の取り組み -子供の成長に感動した場面を共有する-

この園では、毎月1回、園長や各保育士のほか、用務員も参加して「保育自慢会議」を行っています。
「保育自慢会議」を始めた理由として、こちらの保育園の園長は次のように語っています。「これまでも指導計画会議を月に1回行っていましたが、保育を振り返り改善点を指摘しあう会議はどうしてもネガティブなイメージになり『次はこうしていきます』という報告になりがちです。それが次に繋がるかというとなかなか難しいこともあり、会議の有効性が見い出しづらいこともありました。」
そのようななかで、「人間ってマイナスな部分は目につくけど、いいことは意識しないとなかなか目を向けることができないもの。もっと『いいところ』に目を向けよう!」という考えのもと「保育自慢会議」が始まりました。
振り返ってみると初めの頃は遠慮しがちな報告で内容もどこか淡々としていましたが、取り組みを開始してから5年が経ち、継続していくにつれて、職員も子供たちのいいところを見つけようという意識が強くなり、会議の内容も次第にグレードアップしてきました。発表時間は各クラス3分以内でという決まりを設けたことで、3分以内で要点をまとめて発表する力もついてきました。

「保育自慢会議」では、保育自慢の前向きな発言が多く、「それはそのままでいいじゃない。もっとこうしたらこんな風に展開していくよ」といった他の保育士からのアドバイスは、保育士自身の自信や、意欲、やる気の向上に繋がっています。比較的小規模なこの保育園では、クラス担任制ではあるけれど全クラスの担任のつもりで保育するという気持ちで保育しています。「保育自慢」で子供の様子も共有しているので、どのクラスに入っても子供一人一人のことを理解して保育ができるようになりました。例えば、他のクラスの保育士から「今日、Aちゃん、こんなことがあったよ」と子供の様子を報告してもらうことで、「そんな面があったんだ」と、担任だけでは気付かなかった面を知ることができ保育に還元することができます。
「保育自慢」の一例を紹介します。
園庭で野菜を栽培していた時のこと、おいしい実がたくさん採れるように「芽かき」と言って何本か枝を剪定しました。1人の子が、切った枝を水の入った器に「ぽちょん」と入れておいたら、根っこが生えてきました。これを植えてみたらどうなるんだろうという話になって、そこで職員も一緒になっていろいろ調べ、それをポットに入れたらすくすくと育ち、初めに植えた時よりも大きな実がたくさんなりました。全園児が食べることができ、育ててくれた子にみんなで「ありがとう」とお礼を言うと、その子供は得意げに「まぁねぇ」というような表情を見せてくれました。
子供の何気ない行動から新たな発見があり、それを保育士や職員が見守り発展させていく、子供の興味関心にじっくりと付き合うことで、子供の自信に繋がった保育自慢の事例です。

このページをシェア