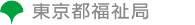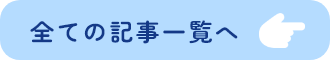第28回 記事子供の意思を尊重する保育
セミバイキング形式の昼食

こちらの園では、食事やお昼寝、手洗いなどの活動は、子供たちの意思によって行われています。特に、子供が自分の気持ちや考えを自覚し、それを表現している3、4、5歳児の昼食の場面を見てみましょう。
昼食はセミバイキング方式がとられ、食べたい子から順に自分で食べられる量を伝えて給食を受け取っていきます。座席は自由で、特にグループは固定していません。毎日隣の子が違うということも多くあります。異年齢の様々な交流の中で、隣の子が食べているものを自分もちょっと食べてみようと苦手な食材を克服できたということが自然に出てきます。
保育士は離れた場所から見守っていて、何かこぼしてしまった時に拭くのも、食器を下げるのも子供たち自らで行います。残飯も食器も、決まった場所に上手に戻していきます。時には5歳児が小さい子のお手伝いをする様子も見られます。
乳児クラスにおける主体的な活動の尊重

幼児クラスだけでなく、乳児クラスにおいても子供自身の意思を尊重しています。2歳児は3、4、5歳児のすぐ隣のスペースで食事をし、少し年上の子たちの食事の様子を見ていました。2歳児も配膳は自分たちで行っています。大きい子たちの姿を見て学んでいるのです。
食事の後のお昼寝においても同様です。お昼寝をするのかどうかも自分自身で選ぶことができ、お昼寝をせずに静かに過ごすことを選ぶ子供もいます。様子を見ていると、0歳児でも準備ができた子は、タオルケットを持って自分でコットに向かっています。最初は自分で行えるようになるまで時間がかかるそうですが、ここで保育士がじっと見守り待つことが大切だとおっしゃっていました。
こうして乳児クラスにおいても、保育士のサポートを受けながら、基本的には身の回りのことを自分で行う習慣を身につけていきます。外から帰れば自分で脱いだ上着をしまい、食事の前には手洗い場に立ち、手を洗います。子供たちが自ら主体的に活動する土台が出来ているのです。ただ、まだまだ未熟な部分も多々あるため、保育者はいつも一人ひとりの子供たちの成長や発達を見極めながら都度サポートしています。その様子から、それが保育の専門性なのだと感じました。
このページをシェア