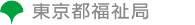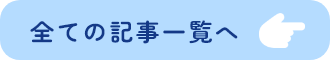第29回 記事保育士の担当年齢を超えた連携
保育士の担当年齢を超えた連携

この園は開設から5年が過ぎようとしている園です。開設当初は新卒や若手の保育士が多い状態から保育が始まりました。園長は当時を振り返り次のようにお話しされます。
「はじめの頃は、毎日子供との対応に追われて、保育士同士が落ち着いて話し合う時間をとることが難しい状態でした。この園の経営法人はほかにも多くの園を運営していることから、保育士を対象に多くの専門研修を実施しています。保育士たちは、積極的に研修でも学びながら、年齢ごとの発達を捉え、保育士が子供と関わるうえで大切にすることはどんなことなのかなどについて考えることが定着してきました。他の園で保育士が積み上げてきた実践例なども参考にしながら、私たちもいろいろ実践を重ねてきた5年間だったと思います」。
こうしたなかで、保育士が、子供の情報を共有することがいかに重要なポイントになるかを意識したことから、毎日、5分でも10分でもミーティングをして、保育士間で目線を合わせた子供の情報を共有する取り組みを進めてきました。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」※ を意識すると、乳児クラスから幼児クラスまで一貫して保育が引き継がれていくものだと考え、保育士は担当年齢を超えて連携し、子供の情報を共有しながら共通理解を図っています。
保育士たちが全員で連携を大切にしながら進めてきた5年間を振り返り、1歳から5歳に育つ過程を見てきた子供たちが、この園から初めて巣立っていきます。園長は子供たちの姿を思い、感慨深いと言います。
年長児の育った姿

この園では3、4、5歳児は異年齢保育をしています。この日3、4、5歳児クラスは公園の広場に出かけました。子供たちは保育士に誘導されながらも、時々車が通る路地を安全確認しながら並んで歩きます。3歳、4歳、5歳の異年齢なので、年長の子供が年少の子供と手をつなぎ、列になって歩いて行きます。工事現場の横を通り過ぎた時、真剣な表情で何か打合せをしていた工事現場の人たちが、子供たちの姿に気が付くと、笑顔になって見守っています。
広場につくと、遊んでよい場所について子供たちに話し、準備体操をしてから鬼ごっこが始まりました。年長児が逃げる側になると、走り出す子供を追う保育士は全力疾走します。「本気を出して子供たちと楽しむことで遊びの楽しさが子供たちに伝わります。それが保育だと思い、どんなことでも全力で対応しています」と、担当保育士は言います。
乳児期から幼児期に育った子供たちには、保育士との関わりを通じて、自分自身で気付いていなかった気持ちに気付くようになる場面があるといいます。例えば登園直後にご機嫌斜めな子がいたときに、保育士は子供自身でその感情の理由を紐解くヒントを引き出すことがあります。年長児との関わりでは、その子に落ち着いてひとりで考える環境を整えてみます。すると「朝ご飯にお米が食べたかったのにパンだった」「お昼寝のブランケットはふわふわのタオルが良かった」など、子供自身でモヤモヤの原因に気が付いていきます。子供自身がその気持ちを保育士に伝え、保育士がその気持ちに寄り添うことで、子供のモヤモヤした気持ちが収まります。そして年長児になると次第に子ども自身が「今日はママとけんかしたから、ちょっとひとりになりたい」と言い、隅にあるソファーで黙々と絵本を読んでいる姿などもあります。モヤモヤしたときの気持ちの処理の仕方をだんだんと身に付けていきます。
※「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量・図形、文字等への関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
(参照:保育所保育指針|平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)
このページをシェア