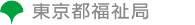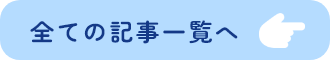第4回 記事専門性を高め続けるための取組 -自分の保育を客観的に振り返る-
自分では気付いていなかった課題に気付く

こちらの保育園では、保育士の専門性を高めるために、年に5回ほど、各クラスの保育の様子を他のクラスの保育士がビデオで撮影しています。これにより、保育の様子を客観的に振り返ることができるためです。
ある日、乳児クラスで保育の様子を振り返るためのビデオ撮影が行われていました。保育室には、子供たちの年齢や興味に応じたおもちゃが豊富にあり、保育士は子供たちの遊びをサポートしながら見守っています。そんな中、ある保育士は子供たちに遊びを通じて豊かな経験をしてほしいという想いから、「このおもちゃはどう?」「こっちのおもちゃも楽しいよ」と様々なおもちゃを子供たちの目の前に出していました。
動画撮影後に、保育士同士で保育を振り返っていたところ、別のクラスの保育士が、おもちゃを出している保育士の様子を見て、「子供が自分でおもちゃを選ぶ前に、保育士がおもちゃを与えている」ということに気付き、振り返りの中で共有していました。おもちゃを出していた保育士としては、遊びを通じて育ちを支えたいという想いで行っていたことでしたが、別の視点で見ると、子供たちがおもちゃを主体的に選ぶ機会がなくなっているという捉え方が出来ることに気付きました。
このように、客観的に保育を見つめることで、自分では気付いていなかった課題に気付き、改善していくことが出来ます。そして、このような取組を通じて気付いた課題は、園全体での課題として捉え、園全体で改善に取り組んでいくのです。
子供たちの遊びの様子から保育を振り返る

また、別の日には幼児クラスで子供の遊びの様子を撮影し、保育士の関わり方や環境作りについて振り返っていました。
こちらの保育園では異年齢保育を行っていますが、クラスのなかで5歳児が十分にコミュニケーションをとりながら役割遊びが発達している場合、クラス全体のコミュニケーション能力が高まっていくということがみられます。幼児期には、友達とコミュニケーションを取り、相手の出方を見て自分のふるまいを決めるという経験も重要になってくるため、保育士は、子供たちの間でそのような遊びが発展しているか、そのために保育士は関わり方や環境づくりを工夫出来ているかを、動画を通して振り返っています。
このように、自分の保育を客観的に振り返り、保育士同士で話し合うことで、保育士は現在行っている保育を「ゴール」として捉えるのはなく、絶えず専門性の向上に努めているのです。
このページをシェア