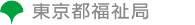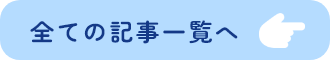第5回 記事子供の主体性を育む保育 -子供たちに芽生えた興味をさらに深める環境づくり-
子供たちの興味の芽生えを育む保育士

ある日、4歳児の子供たちは散歩中に、水中でクネクネ動く不思議な生き物を見つけました。子供たちは、初めて見るこの生物に対して、「なんていう生き物なんだろう?」と興味津々です。保育園に戻ってからも、散歩中に出会った不思議な生き物のことが気になっていました。
保育士は、子供たちの生き物に対する興味が芽生えていることを一早く察知し、子供たちの興味が冷めないその日のうちに、その不思議な生き物と似ている写真を何枚か用意しました。
子供たちは先生の用意した写真を夢中になって見ています。写真を見ていた子供が「これかな?」と1枚の写真を指差して言います。それを聞いたほかの子供が「いや、これより長かった」と記憶をたどりながら、細長い姿をしていた生き物の形を思い出しています。
子供たちは、散歩で見た生き物の特徴を目の前の写真と比べて話し合う中で、この生き物はウミヘビではないかという結論に達しました。この生き物が実際にウミヘビかどうかは確かめられなかったのですが、その真偽よりも、子供たちが図鑑を見て考えをめぐらすことを保育士は大切にしました。
「自分たちで出来た!」という達成感

そんな楽しそうな4歳児の様子を興味津々で見ていたのが、3歳児たちです。生き物の正体を探る遊びをしているうちに、水中で暮らす生き物への興味が広がった子供たちは、3歳児と4歳児で一緒に、水族館ごっこをすることになりました。
水族館ごっこでは、半透明の青いブルーシートを窓や天井に貼り、壁や天井には海の生物の絵を飾りました。ブルーシートを通して部屋の中に光が入ってくることで、保育室はまるで水中にいるような雰囲気になりました。これらは子供たちのアイデアです。
保育士は、子供たちの「やってみたい!」という気持ちを尊重するために、ハサミで複雑な魚の形を切る時など、どうしても手助けが必要な時だけサポートし、それ以外の場面では子供たちの様子を見守っていました。子供たちは3週間をかけて自分たちの水族館を完成させます。共通の目的に向かって自分たちの力で試行錯誤を重ねたことが、自分たちで創りあげたという達成感や誇らしさにつながりました。このことは、その後の活動への原動力にもなります。
保育士は子供たちの興味の芽生えに気付き、その興味を深めるためのきっかけを提供し、子供たちの奮闘に伴走し、子供たちの育ちを支えているのです。

このページをシェア