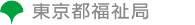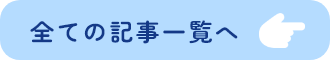第6回 記事子供の気持ちを受け止める保育 -意欲の芽生えや情緒の安定を育む-
気持ちを受け止めることで、子供に芽生えた意欲を育む

保育士は、日々の保育において、子供に芽生えた意欲や興味の芽を大きくできるように、子供たちの気持ちや行動を受け止めるということを大切にしています。
例えば、ある2歳児クラスの子供は、身体機能が発達し行動範囲が広がるとともに、これまでできなかった遊びに挑戦したいという意欲がわいていました。
そんな中で、机に上るという遊びを見つけます。大人目線で見ると、危ないのでやめて欲しいと思う行動ですが、その子はこれまで上れなかったところに上れて楽しそうでした。
その子が机に上って遊んでいることに気付いた保育士は、まずその子の「上りたい」と思う気持ちを受け止めました。そして、その上で、机に上るのが危険であることや机に上らない理由を丁寧に伝えます。
また、その保育士は、その子が高いところに上る力がついたという成長に気づきました。そして、その子の「高いところに上りたい」という気持ちを、別の方法で満たすために、「あそこに上がれる場所を作るから、あそこで遊ぼう」と子供の欲求を満たす保育環境を設定していました。
そうすることで、保育士は、「高いところに上りたい」というその子の興味の芽を摘むことなく、それを発揮できる別の環境を提供することで、子供たちに芽生えた意欲を育んでいるのです。
気持ちを受け止めることで情緒の安定へ

子供の気持ちを受け止めることは、子供の自己肯定感や情緒の安定にもつながります。
例えば、1歳児は、子供同士のトラブルで「かみつき」が起こりやすい時期でもあります。
ある時、「かみつき」をしてしまった子がいました。保育士はその子に、噛みついてしまった理由を丁寧に聞いています。その子は、友達の持っていたおもちゃを指差して「あれ」と言っています。体を押される状況もあったようです。かみつきの理由を理解した保育士は、まずその子の気持ちを受け止めて、理解していることを伝えます。
「おもちゃが使いたかったんだね」「押されたのが嫌だったんだ」と気持ちを代弁し共感することで、その子も少しずつ気持ちが落ち着いてきました。その上で、保育士は「おもちゃを貸してって言うとよかったね」と他の表現方法や、「噛まれたお友達は痛かったみたいだよ」と相手の感情を伝えます。
この時期の子供は、言葉で表現するのが難しい場合もあるので、保育士がその子の気持ちに共感し、適切な言葉で代弁することで、子供たちは言葉を通じて自分の感情を伝え、相手の気持ちを理解する力を養います。
保育士は子供の気持ちを受け止めて、共感や代弁をすることで、子供たちが自分の気持ちを言葉で表現し、自己肯定感や情緒の安定を培うという育ちを支えているのです。

このページをシェア