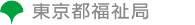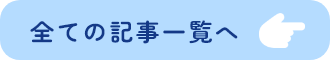第8回 記事他者との違いを受け入れる -友達との関わりを通じて社会性を育む-
自分の思い通りにならないことを知る

保育士は、子供たちが遊びの中で時には自分の思い通りにいかなかったり、友達等との間でいざこざが生じたりするなどの葛藤を体験していく中で、他者との違いを受け入れ、社会性を身に付けるという育ちを支えています。
例えば、0歳児はおもちゃの取り合いをよくします。この時期は、それほど執着しないので、保育士が他のおもちゃを側に置いておくと、おもちゃを取られた方はすぐ気持ちを切り替えて、他のおもちゃで遊びます。自分の思い通りにならない他の存在を知ることで、少しずつ自分の気持ちに折り合いをつける力が身につきます。このような経験の積み重ねが、これから社会の中で生きていくうえでとても重要です。そのため、保育士は必要以上に関わらずに見守っています。
また、子供が思いどおりにならなくてひっかいたり、噛んだり、叩きそうになった時は、保育士が関わり、すぐ止めます。保育士は子供たちの様子を見守り、どのタイミングで関わったらよいのかいつも模索しています。子供によって対応方法が異なるのでそこを見極めることが難しく、保育士の仕事の面白さでもあるのです。
また、この園では3歳以上の子供同士で喧嘩になったときに、「ピーステーブル」を使います。激しい言い合いや、おもちゃの取り合いが起こった時、このテーブルのある場所に移動して、向かい合い、話し合いを行います。このテーブルに移動することで、熱くなっていた子供たちの気持ちが、少し落ち着いて、テーブルに着くことで少し冷静になって相手の意見を聴くことができます。自分の意見を相手に分かるように話すこと、相手の意見を聴くことで自分の思い通りにならないこともあると、理解していきます。保育士は適度に関わり、できるだけ子供同士で解決できるように見守ります。
保育士の見事な対応

保育士は、子供たちが他者を理解したり、多様な視点に立って物事を理解したりする育ちも支えています。
例えばこちらの園では、5歳児をグループに分けて、四つん這いになって行う雑巾がけを行っています。体幹を鍛えることもできるので、運動会のレースにもなっています。うまくできたグループには、金のシールが配られ、何枚か集まると新しい緑色の雑巾がもらえます。ある時、緑色の雑巾がもらえたAちゃんが、Bちゃんにちょっと自慢げに話をしました。Bちゃんはちょっと悔しかったのか保育士に「Aちゃんが私に自慢してきた」と話をしました。保育士は、この時、一瞬考えてから「きっとAちゃんは嬉しかったから、その気持ちを報告したんじゃない?」と対応しました。Bちゃんは「そうか、嬉しかったのか、分かった」と納得したようにうなずきました。
このとき保育士が「緑色の雑巾をもらえるようにあなたも頑張って」と対応していたら、競争心をあおることになります。Aちゃんの言動の受け止め方について、保育士が「自慢」ではなくて、「嬉しかった気持ちの報告」という違った受け止め方を伝えたことで、BちゃんだけではわからなかったAちゃんの気持ちに共感することができたのです。保育士の見事な対応です。
このページをシェア